| �� �� �� �� |
���U�� |
�� �� �{ �� �� |
�s�{���s |
��@�@�@�@�@�� |
���@�@�@�� |
�v�@�@�@�@�@�@�| |
|
�@�@ |
��
�P
��
��
�� |
�l
��
�m
��
��
��
��
��
��
��
��
�n
�� |
1 |
�������w�@��w�@���L�����p�X�@�@�@9101���� |
���� |
�u�Ȃ��܁v�E�E�E�����悭�A�������悭�A�����ނ��I�I |
�}����s�������ۈ珊 |
���\���邱�Ƃ���肾����5�Ύ�A����𒆐S�ɐ��������H�B�ɉ������ڕW�ݒ�̏d�v���ɋC�Â��A�ۈ珊�S�́A�ی�ҁA�n��ƂȂ���A��������̔��\�̏���o�������Ă����܂����B�Z���t���b�Z�[�W�����߂邽�߂ɗl�X�Ȏ�g���s���AA����݂̂Ȃ炸5�Ύ��S�̂����ɍ��܂���1�N�ԂɂȂ�܂����B |
| ���Q |
�u�ڂ��̂Ƃ������I�v�`���ǎ��Ƃ̂������̂Ȃ��Ł` |
�w�Z�@�l���U���I�w����t�c�t�� |
�\��邱�Ƃł���������\���ł��Ȃ������^�_�V�N���A�����̂��镔����L�����ƂŁA���炪�����Ă�������������Ƃ��ł����B�^�_�V�N��ς��悤�Ƃ��Ă������́A�ނ������炵����������@���ꏏ�ɒT���Ȃ��ŁA�l���F�ߍ����Ȃ��邱�Ƃ̉�������������ꂽ�B |
| ���� |
�݂ɔF�ߍ����A���Ɉ炿�������ԂÂ���`�^�b�`�œ`���v���` |
��s���Y�c�t�� |
�c����������荇�����Ƃ��Ƃ����āA�F�B�̎v���������A�撣���F�߂钆�ŁA���ʂȎx����K�v�Ƃ���c�����A�w���̈���Ƃ��āA�[�������C�����ŗc�t�������𑗂邱�Ƃ��ł��钇�ԂÂ�����߂����Ď��g��ł����B |
| ���{ |
�ǂ�Ȃ��������������`�s���̗��ɂ���@���̎q�́u�悳�v�ɂ�������ā` |
�����s���z�E���w�Z |
�F�����ƂȂ��ꂸ�A�g���u���������Ă������`�B�`�̂���C���������݁A�c�Ȃ��݂̂a�����Ɩ{����`�������A�Ȃ���������Ă����B���̒��ŁA�a���`��M���Ď����̃��[�c�ɂ��Ęb���A�`�͂a���x����悤�ɂȂ����B |
| ���� |
�u�ۈ牀�ɍs�������I�v�`�o���̐ςݏd�Ȃ肪�h���M�h�ɂȂ�����A�����A����̕�e�ւ̃A�v���[�`�` |
�c�ۈ�̉��{�݁u��܂̂��Ђ�v
�@��Îs���Ђ������ۈ牀 |
�����E�V�т̌o�����R�����A�o���������Ȃ������r����B�o����ςނ��Ƃłr���ς��ƐM���ĕ�e�ɃA�v���[�`���A�ۈ�҂ƕ�e���肢���ɂ��Ăr����ɂ���������B��q�Ƃ��ɕϗe������ꂽ���Ƃ����B |
| 2 |
���s����������w�Z �@�̈�� |
���� |
�u�����킹�̃o�P�c�v���ӂ�ӂ킱�Ƃł����ς��ɂ������I�w�l������̎�����`�u�������v�����ւ̑Ή��Ǝw���`�x�����p�������H |
�����s���}�y���w�Z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�����s�ł́A��Q�ҍ��ʔ���������������ۑ�Ƃ��Ă����B�ۑ���������邽�߂ɁA�s����ψ���́w�l������̎�����x���쐬�����B�}�y���w�Z�ł́A������̋��ނ����ƂɁA�q�ǂ��̌���������ƂÂ����i�߂Ă����B���̎��H�̋�̂Ǝq�ǂ��⋳�E���̊w�т����B |
| ���m |
�uA�@�������A����Ă݂�v�`A�Ƃ̂�������ʂ��Ċw���Ɓ` |
����s�����Õۈ珊 |
�q�ǂ���ی�ҁA��l�ЂƂ���ɂ����ۈ�Ƃ͉������l���A���ԂÂ���ւƎ��g��ł���B4�Ύ��AA�Ƃ̊ւ���ʂ��A��������\���ȂǕۈ�҂��w���Ƃ�������B |
| ���R |
�u�����Ă��������v���߂Ă���������b�Z�[�W�`�A�C�ƕ�e���狳���Ă������������Ɓ` |
����s�������ꏬ�w�Z |
�w�Z�Řb�����Ƃ��ł��Ȃ��]�Z���̃A�C�B���ɏo���Ȃ��z����m�邽�߂ɉ����ł��邾�낤�B�v���Y�݂Ȃ���J��Ԃ����ƒ�K��ŁA�A�C�̋C�����ƕ�e�̑z���ɋC�Â��A�����g�����炩�ɕς���Ă����܂����B���߂Ă̓]�Ō˘f�����肾���������u�A�C�����邩�炪����I�v�Ɖ߂������u�ЂƂ�ڂ������o���Ȃ��w���Â���v���߂��������H�ł��B |
| ���{ |
����ǂ����́A����ǂ����Č����Ă����˂�Ł`�q�ǂ��E�ی�ҁE�w�Z�̂Ȃ�����Ɂ` |
�����s�������쏬�w�Z |
�E�w�Z�i�w���j�ɂ́A���܂��܂ȉƒ����x���̕K�v�Ȏq�ǂ�������B����Ȏq�ǂ������ɁA���E���i�S�C�j�Ƃ��Ăǂ����������Ă����A�ی�҂ɂǂ̂悤�Ɋ��Y���Ă����̂��B�E�w�Z�ƒn��Ɖƒ�̘A�g�̑���B |
| �ޗ� |
�u�搶�̂�����Łv�`A����Əo����ā` |
�V���s���O�͏��w�Z |
�͂��߂Ă̌���Ŏq�ǂ������Ƃ̕t���������Ɍ˘f���A���Ƃ��X���[�Y�ɐi�܂Ȃ������������B����A����͗����������A���ƒ��̗������������������B�����A����́u�搶�̂�����Łv�Ƃ������t�ō����Ă����͎̂��ł͂Ȃ��AA���ƋC�Â����ꂽ�B�����g�ƃN���X�̕ϗe��`�������B |
| �O�d |
���������������ā`�`����C���������߂���M�̕�Ƌ��Ɂ` |
�ɉ�s���ѐA�ۈ牀 |
�u���ʂ����ق��ɂ��A����ق��ɂ��Ȃ��Ă����v�u�n��𖼏���q�ɂȂ��Ăق����˂�v�ƁA�q�ǂ��̏����╔�����ʉ����ւ̊肢�����ɕی�҉�����Ƃ��Ċ�������M�̕�B����A�q��Ăɕs����������̑��݂Ɖ�����퐶���̒��ʼnۑ�������M�̎p����AM���u�����͑�ɂ���Ă���I�v�Ǝ������邱�Ƃ��ł��A��̊肢�ɉ������鑶�݂Ƃ��Đ����ł���q��Ăɂ��āA��Ɣ����^�̎x���Ɏ��g��ł���o�߂����B |
| 3 |
���s���Z�g���w�Z�u�� |
���� |
����Ă݂悤�������w�K�`�����Ă��������ő�ɂ��������Ɓ` |
���ˎs���c�����w�Z |
�������x����J���̎�A�����Ď�̂ʂ����肩����߂Ēm��u�Ƒ��̎v���v�A�����������ɕ������w�K���n�߂܂����B���j�w�K�▽�����߂�w�K�Ƃ��d�˂āA�q�ǂ������̊w�т́A�u�����Ă��������ő�ɂ��������Ɓv�ɂȂ����Ă����܂��B |
| ���� |
�ӂ邳�ƂɌւ�������Đ�����`��y�̐���������w�сA���Ȃ�U��Ԃ萶�������l����` |
�߉꒬���ؓ����w�Z |
�l�X�ȍ���Ɠ����Ȃ�����ӂ邳�Ƃ������A�ӂ邳�Ƃ�ς��悤�Ƃ��Ă����y�̐���������w�B���̐��������玩�Ȃ�U��Ԃ点�����������݁A�ڕW�������Đ������悤�Ƃ���ԓx��A���ԂƋ��Ɏ��������̂ӂ邳�Ƃ����悭�ς��Ă������Ƃ���s���͂�|���l���w�K�̑n���Ɏ��g��ł����B |
| ���s |
���Ɉ���ĂȂ��낤�H�`�e�c�ƒ��Ԃ���w���Ɓ` |
�s���Z�g���w�Z |
�҂́A�p��̎��Ƃ̎��ԍu�t����A�x���S���̏�u�t�ɕς��q�ǂ������Ɗւ�邱�ƂɂȂ����B���ꂩ��5�N�Ԃɂ킽��u���w���ۏ�Ƃ͉����v���v���Y�݂Ȃ���A�n��̕�����̎w�E��A��y��������̃A�h�o�C�X������A���k�̌��t��s������w�肵����g�̕B |
| �ޗ� |
�Ԃ邱�ƂłȂ��w���Â�����`�u����g�فv��A�Əo����ā` |
�c���{�����c���{���w�Z |
�u����g�فv��A���A�ꖇ���W�u���̂Ȃ��݂�ȁI�v�ɁA�����̓��L���ڂ��Ă݂�Ȃɓǂ�ł��炤���Ƃ�O��ɁA�͂肫���ē��L��Ԃ��Ă��Ă��ꂽ�BA�ɂƂ��āA����̂܂܂̎��������炯�o����ꂪ����A������~�߂�݂�Ȃ����āA�Ȃ����Ă����B���̉ߒ������B |
| ���s�s |
�N�����h������܂��h�ɑ��݂ł��鋏�ꏊ�Â�����߂����� |
���s�s�y�������� |
���l�Ȏq�ǂ��������킹��y�������فB���̓���͌����ĕ����Ȃ��̂ł͂���܂���B���ׂĂ̎q�ǂ��́h������܂��h��ۏႷ�邽�߂ɂ͂ǂ�����悢�̂��B���̂��Ƃɂ��āA���ق̂���݂�Ҏ��g�̃o�b�N�O���E���h�Ɗ֘A�t���Ȃ�������Ă��������܂��B |
| �O�d |
�u�݂�Ȃ����̂��ƌ����Ȃ��v |
����s�����a���w�Z |
A�́u�F�����Ȃ�Ă���Ȃ��v�u�����̋C�������킩���Ă����l�́A����ւ�˂�v�Ƙb���Ă����B�u�����̂킩���Ăق������Ɓv���o��������W�A������Ƃߍ�����W���߂�������g�����B |
| 4 |
���s����g���w�Z �@�̈�� |
�F�{ |
�u��������A�����ȁ`�B�ڂ����������āA�ΐ삳��̂Ƃ���ɍs�������I�v�`������ƕ��e�̌�肩��` |
�F�{�s���������w�Z |
������e�q�̏o�����̒��ŁA�Ƒ��̂����ȁA�w�K��̑f���炵�����w�ԕҁB���̉c�݂̒��ŁA���g�̉Ƒ������ߒ����A���̌ւ���������A���̂��Ƃ��炵�̎��Ƒn���ɂȂ��Ă������B |
| ���m |
�Ȃ���̂Ȃ��ł����₢�ā`A�̊肢�����߂ā` |
���m�s���`���w�Z |
�l�Ƃ̊ւ��ɉۑ������A�ْ������l�q�Ŋw���т炫���}����2�N����A�B.�l���w�K�����ɂ����Ȃ��܂Â��肪A���ǂ̂悤�Ɏx���Ă������̂��BA�ƂȂ��鎅����͍����Ȃ���AA�̎v����肢���݂Ƃ�A�S������ł����܂ł̎�g�����B |
| �_�ˎs |
�Ί�̌������ɂ�����̂́`�l�Ƃ̏o���ʂ��Đk�Ђƌ��������q�ǂ������` |
�s�����召�w�Z |
�l�Əo����сA�b�Ɏ����X���邽�тɁA�^�Ȃɐ������ݍ��ނ����Ƃ��A�q�ǂ������͐l�Ƃ��đ�Ȃ��Ƃ��w��ł����悤�������B��_�W�H�ʼn䂪�q��S���������A�����{�Ŕ�Q�ɑ���ꂽ�������ƌ������������Ƃł����̂́E�E�E�B |
| ���{ |
�Ƃ��Ƃ�`�Ƃ��̉ƒ�ɂ�������� |
��s���ː����w�Z |
�w�Z�ł͂Ȃ��Ȃ��f���ȋC�������o�����A�v���Ƃ͗����ȍs�����Ƃ邱�Ƃ������`�B���̂`�����Ԃ⋳�E���Ƃ̂������̒��ŕϗe���Ă����l�q�A�܂�������x����Ƒ��̕ϗe�̗l�q�ɂ��ĕ���B |
| ���� |
�u����Ă����傤���Ȃ��v����u����Ƃ��傤���Ȃ��v�� |
�b�ǒ����b�Ǔ����w�Z |
�������Y�����Ȃ��Ȃ����肹���x���������`���B���̌����͂`�������ɂ���킯�ł͂Ȃ��B�������x���̐ӔC�͑S�Ď����ɂ���Ɗ����Ă���B�`���̊����Ă��镉�S����菜���Ȃ�����A�ӔC�����������Ǝ��g�݂܂����B�����̒��ł`�����������h��ɑ��āu���Ȃ��Ƃ��傤���Ȃ����A����v�̈ꌾ�ɂ͂`���̋����C�������������B�����g�����̎��H��ʂ��đ����̂��Ƃ��w�т܂����B |
| ��� |
�u���₾�A�ł��A�y�����B�E�E�E�Ђ݂B�v |
�F�J�s�����䏬�w�Z |
�q�ǂ����������Ȃ�Ƃт�ʂ��č��a����ƂȂ����Ă����B����Ȏq�ǂ��������x���ł�������ς����̂́A�F�{�ł̌[�q����e�q�Ƃ̏o������������炾�B�����̐S�Ɍ������������Ƃ��q�ǂ������ƂƂ��ɑ�ɂ��Ă��������B |
| 5 |
���s���ؒÒ��w�Z�̈�� |
���� |
�u�F�߂�v�Ƃ������� |
�O�ؒ������R���w�Z |
�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��ƍU���I�ɂȂ�A����BA���A���S���ĉ߂�����w���Â���ɓw�߂��B�������A������A����Ƃ�����낤�Ƃ������̐�������A�Ǘ�����������悤�ɂȂ�B���A�u�݂�Ȃƈꏏ����Ȃ��ƈӖ����Ȃ��v�ƂȂ��܂Ƃ��āA�������邱�Ƃ�~����悤�ɂȂ����B�F�߂�Ƃ������Ƃ́A���݂��̐������v���Ȃ��炩����荇�����Ƃ����ȑԓx�ł���B |
| ���s |
�䂤�Ɖ߂������Q�N�ԁ`�u��l���y��˂�v����u�ō��ł����v�܂ł̓��̂�` |
�s����Տ��w�Z |
��������Ƒ��l�������A�Ȃ��Ȃ����������Ċw�Z�����𑗂邱�Ƃ��ł����ɂ����q�ǂ��ɑ��A����5�N���̒S�C�Ƃ��đ��Ƃ܂�2�N�Ԋւ�����B�Ǘ��������ł������{�l�ƏW�c�Ƃ��Ȃ��A�u�ō��ł����v�Ƃ������t���c���đ����܂ł́A�w���W�c�Ɋ��u�����l�X�Ȏ��H�̕��s���܂��B |
| ���s�{ |
���ȑ��݊������߂�w���Â����A�̐��� |
�v��R�������p���w�Z |
�\���A�\�́A���ƃG�X�P�[�v��p�j�A�함�j���ȂǗl�X�ȉۑ���������������B�w���ł̋��ꏊ�Â���̎��H�Ɖƒ�A�g��i�߂钆�Ŏ��ȑ��݊������߂Ă������B���ȑ��݊������܂钆�ŁA�l���I�Ȋ��o�̐���������ꂽ�B |
| �O�d |
�uA�@�A�y�ɂȂ肽�����v |
�u���s���镔���w�Z |
���e���]�[�ǂœ|��Đ�������ς���A�B�����Ƀ��n�r�������镃�ƕ����x�����B�S�z���Ȃ��猩���A�ƉƑ��B����Ȓ��ŁA�Ƒ��̎v��������Ⴄ�o�������N����BA�́A5�N���̓��L�ɏ��߂ĕ��e�̂��Ƃ�Ԃ�B�ƒ�K��ŁA���e���|��Ă���̕��e�ƕ�e�̊�����A�ƂƂ��ɒ������Ă��������AA�͗��e�̖{���̎v�������߂Ēm��BA���ς��A����̎q�ǂ��������ς��B������A�̕����A�ꂪ�ς���Ă����B |
| ���� |
���֊J��Ǝ� |
���q�������q��ꏬ�w�Z |
���֊J��͉ߋ��̂��Ƃ������B���֊J������p����̉���Əo��A�A���ґ勴����Əo������B���֊J��͎����g�̖��ł���A�����Ő�����q�ǂ������̍��̖��ł���A�����ւȂ�����ł��邱�ƂɋC�Â��B |
| 6 |
���s�����̗����w�Z�̈�� |
���� |
������肠YELL |
�v���Ďs���P�������w�Z |
�P�������w�Z�ł́A�l���J���L�����������ƂɁA�e�w�N�̌n���������������l���w�K�Ɏ��g��ł���B�q�ǂ����m���Ȃ��邽�߂ɁAA���𒆊j�ɐ����A�����̎v������邱�Ƃ��ɂ����w���Â�����߂����Ă���B |
| ���m |
�u�����ɂ̂�����v |
���m�s�����q��w�Z |
�S�苭���^���ɂ���Đݗ����ꂽ�u��Ԓ��w�Z�v�E�u��t�ۈ牀�v�E�u���q��w�Z�v�̂R�̎{�݂Ɋւ���Ă����l�тƂ̋��ʂ̎v����肢���u�����ɂ̂�����v�Ƃ��A����ɍ������͉������Ă���̂��Ƃ������_�ŁA�q�ǂ������́A�������g�����ߒ����Ă����B |
| ���s |
�����������ɁA���߂�ꂽ�v���E�E�E�`�n�拳�ނ���w�l�x�Əo��Ȃ��������́w���炵�x�Əo��Ȃ����` |
�s�����쏬�w�Z |
���N�T�N���Ŏ��H���鎩��Ґ����ށu�܂�݂͂�Ȃ̂����v�B�����Ă���Q�O���N���o�����A�����̐��_�������p���A�ēx�Ґ��Ɋւ�����l�����Ǝq�ǂ������Ƃ��o��킹�邱�ƂŁA���ނ̍���𗬂��u�����������v�Ɍ������킹�����H�B |
| �ΐ� |
�݂�Ȃ̂Ƃ���ɍs�������Ȃ��A�����ǂ݂�Ȃƈꏏ������ |
����s���������w�Z |
A����3�N�̂Ƃ�����ւ��A5�N���œ��ʎx���w���ЂɂȂ�Ƃ��A�ꏏ�ɓ��w�S�C�ɂȂ����BA���u�Љ�ɏo�A���̑O�Ɏ��ʂ��B�v�ƌ��������A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�����w�ɍs����A���u20�ɂȂ�����E�E�v�Ƃ������v���o���A�A�����Ă����̂��y���݂ɂ��Ă���B |
| ��� |
���̒n�����ʂ̂Ȃ��n�Ɂ`�n��Ǝq�ǂ��Ƌ��ɕ��Q�N�Ԃ̑����w�K�` |
�{���s�l�����猤���� |
�u���y���邽�̃}�b�v�v����͂��܂�q�ǂ��̑����w�K�B�w��̓������ɂ��݂����|�c���ƊG�D���P���B�u���ꂶ�Ⴀ�A�n��Ǝq�ǂ����Ȃ���Ȃ����Ⴀ�Ȃ����B�v���̐S�͂��݂����Ȃ����B�����ɂ��C���킢�Ă����B�u���̒n��ɕ����Ƃ����Ɩ����Ă���͂����B�v�q�ǂ���n��̕��⓯���Ǝ���Ȃ��A���ɕ��Q�N�ԁB�����ɂ́A��������Ȃ��قǂ̊w�т��������B |
| 7 |
���s�����W�H���w�Z�̈�� |
������ |
�u�݂�ȂɂƂ��ā@���܂�̗F�����ł��v |
�N�������g�����w�Z |
�u�����̂��Ƃ��������앶�����ʂɓǂ߂�w�Z�ɂ��Ăق����v�Ƃ��������̐e�̊肢���Ƃ߁A�������w�K���͂��ߊw�Z�ł̊w�т��A���ʂɕ����Ȃ��E�����Ȃ��������ɂȂ���悤�S���E���łƂ肭��ł��邱�Ƃ̕ł��B |
| ���m |
�����⎙���ف@�Ԃ̗֎q�ǂ���ELL���w��`�Q�O�P�T�N�x�̊������` |
���m�s�����⎙���� |
�����⎙���قɗ��ق��鏬�E���w���ɂƂ��āA�����قł̓��X�̊������L���Ȑl�����o���{�̏�ƂȂ邱�Ƃ��肢�A�����⎙���ق̂Q�O�P�T�N�x�̗l�q�����ǂ������Ƃ̉�b��A�w�����Ƃ̊ւ�肩����܂��B |
| ���� |
�ӂ邳�Ƃ��ւ�Ɏv���A��̓I�Ɋ���ł��鐶�k�̈琬���߂����ā`�u�m����t for ��߉�v�̎�g��ʂ��ā` |
�߉꒬����߉ꒆ�w�Z |
�قƂ�ǂ̐��k�����ƌ�ӂ邳�Ƃ𗣂��B�܂��A�Q�N��ɖ{�Z�͕Z�ɂȂ�B�ǂ̂悤�Ȋ���ł��ӂ邳�Ƃ��ւ�Ɏv���A�Ջ@���ςɑΉ����A�����܂��������Ă������Ƃ��ł��鐶�k�̈琬���߂����Ď��g��ł��܂��B |
| ���{ |
�u�U�P���ŗǂ������ƐS����v���܂��v�`�R�N�Ԃ̓��X��U��Ԃ��ā` |
�L���s����ܒ��w�Z |
�U�P���ɂ́A�C�ɂȂ�`�������B�������o���Ȃ������`���A�w�Z�E�n��E�ی�҂ŘA�g���Ȃ��猩���A�Ƃ肭�݂�i�߂��B�`�������������̎v�����o����悤�ɂȂ��Ă������l�q����A�u�{�C�v�Ŋւ���Ă���������q�ǂ�����w�B |
| �V�� |
�w�сA�ς��A�s�����Ă��� |
�����s���V�䒆�����w�Z |
�V�䒆�����w�Z�ł́A�P�N�����瓯�a����̊w�K��ς݂�����B�T�N���ŕ�����������V�����A�����z�x���̂m���猋�����ʂ̑̌����A���ʂ��Ȃ����Ă������߂ɂł��邱�Ƃ��l�������w�K�𑱂��Ă���B�����̊w�т�o��A�𗬂�ʂ��āA�q�ǂ���ی�ҁA�n��̕������ʂɑ���l�������ς��A���t���������Ă����B |
| 8 |
���s���W�H���w�Z�̈�� |
�F�{ |
�u�����̕s���Ƃ��A����Ƃ���m���Ă��炦������A�E�E�E�v |
�X�쒬�����k���w�Z |
����q�ǂ���ɒʂ��j�������������A���S�ɂ����Ȃ���A�i�H���J�̎�g���Ƃ����Ď��g���Ƒ����ӂ�Ԃ�Ȃ���A�����ʂ̊w���Â�����߂������B |
| ���� |
�O���[�v���[�N���d�������l���w�K�̎��H |
�����썂���w�Z |
�O���[�v���[�N�𒆐S�ɍs�����l���w�K�ɂ��A���k�̃R�~���j�P�[�V�����͂��傫�����サ���B�b�������̒��Ŏ���̖��������o���邱�ƂŎ������g��m���̎�i�Ƃ��Ȃ�A�S�����Q���ł���z�[�����[�����������������B |
| ���s |
��������́u�z�[���v�̒��Ł`�����������u���ꏊ�v�ň��������` |
�s���W�H���w�Z |
���N�̎�g�����Ă������Łu�z�[���v�Ƃ������t������܂ł̎��H�̃L�[���[�h�ƂȂ�A�W�c�琬�ɂ����āu�z�[���Â���v�������t�Ƃ��Đ��k���������鏬�W�c���d�����Ă����B�w���E�������E��⌤�ł̊����ƒS�C�E�ږ�̉ƒ�ւ̂������A�������������ꏊ�u�z�[���v�Â���̎��H�B |
| �ޗ� |
�w�Z�A�N���X�A�����ǂ��u�z�[���v�ɂȂ�܂� |
�䏊�s���吳���w�Z |
�u�����́w�z�[�����X�x��I�v�l�X�ȉۑ������A���w��������r���h��������Ă���A���A�l�X�Ȏ�g��ʂ��Ă������Ȃ���������ɂƂ��Ắu�z�[���v���ǂ̂悤�Ɉӎ����Ă���������`�������Ǝv���B�܂��AA�̎p��ʂ��Ď����g���w���Ƃ�`�������B |
| ���� |
�������~�ߎn�߂����k�Ƃ̂������ |
���쑺�����쒆�w�Z |
��N�̒�����ŁA�S�C�����Ă������k�̕�e�i�����ҁj�̕����B�u�������~�ߎn�߂����k��O�ɁA�����ɉ����ł���̂��B�v������ɖ₤�����ƂȂ����B���k��Ƒ��Ƃ������A�Ȃ��葱�������B |
| 9 |
���{���ē������w�Z�̈�� |
���� |
�����m��ʐl�̐������Ɋw�ڂ��`�u�Y�z�Ɛl���v�̋��މ���ʂ��ā` |
�喴�c�s��������w�Z |
�Y�z�ʼnh�����喴�c�B���l�A���N�l�A�����l���̌������J���Ŏx�����Ă��܂����B���ׂ钆�ŁA�����l�Ɋ��Y�����������l�X���������ƂɋC�Â��܂����B�^�_���炫���l�X�𒆐S�ɁA���ʂ��Ȃ������Ɨ����オ�����u�����m��ʐl�v�����̐������Ɋw�т܂����B |
| ���� |
���k�̖������������邽�߂̎��H�I��g |
�����x���������w�Z�H�m�Y�Z |
�T�N��ъŌ�t�ے��Ƃ��ĂP�T�ŊŌ�t���߂������w�������k�ɑ��A���Ɛ���㋉���Ƃ̌𗬂��Ƃ�������̏��������C���[�W������ƂƂ��ɁA�̌��I���Ƃ�n��Ƃ̘A�g�ɂ��A���̎�����l�����o�̈琬�Ɏ��g��ł����B |
| ���{ |
�u�������ċ������Ƃ��������ǁA�����Ƃ������Ȃ肽���v�`���̌��t�������ɂ����`�̐����ƁA���̐����` |
�{�����䍂���w�Z |
�ی����ɂ悭��������`�̌��ۑ���Ƃ̊W�A�Ƒ��Ƃ̊W�����Ƃ���A�ƒ�ɋ��ꏊ���Ȃ����Ƃ��ӎu�̎コ�E���s�ׂւ̊�@���̒Ⴓ�ɂȂ����Ă���ƍl�����B�����Ŋw�Z�����Ă̗\�h���炪�K�v���ƍl���A�u���Ɨ������l����g�q�v�𗧂��グ�邱�ƂɂȂ����B�܂��A���̂g�q��ʂ��āA���ȍm�芴�Ƃ���ǂ����ł�����Ȃ����Ȃ₩�ȋ����u���W���G���X�v��g�ɂ��Ăق����ƍl���Ă���B |
| ���s�s |
�n�`�h���̂ЂƂ������@�`�ЂƂ���ɂ���ւ���ʂ��Ċw���E�w�N�E�w�Z�Â�������Ă����{�Z�̎��g�݁` |
�s�����������w�Z |
�{�Z�ɂ͌������w�i��w���킳��Ēʂ��Ă��鐶�k���������܂��B�ߔN�A���k�����͂��܂��܂Ȋ����ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂����A�����ɂ͋��E���́u�ЂƂ�v���ɂ���ւ�肪����܂��B���̂��Ƃ��u�ЂƂ�v�̐��k�Ƃ̊ւ���ʂ��ĕ��܂��B |
| �_�ސ� |
�莞�����Z�@���k�x���̌��ꂩ��`�w�Z�O�̗l�X�Ȏx���҂Ƃ̘A�g�̐��ʂƉۑ�` |
�������l���������w�Z�@�莞�� |
�O���ɂȂ��鐶�k��A���܂��܂Ȑ����̉ۑ���������鐶�k���A�w�Z�O�̎x���̑����E�@�ւ̗͂���Ȃ���x�������g���s���Ă����B���̐��ʂƉۑ�ɂ��ċ��L���A�[�߂Ă��������B |
��
�Q
��
��
�� |
��
��
��
�� |
1 |
���s����K�X���w�Z �@�u�� |
���� |
Like a Rainbow �`���̂悤�Ɂ` |
�c��s�����쒆�w�Z�@ |
�������̔ԑg�uLike a Rainbow�v�i�Z�N�V�����}�C�m���e�B�̔ԑg�j�̐���ߒ��ł̊w�т�o��B���̔ԑg���g���čZ���O�Ō[���������s���Ă������ƁB���̎�g��ʂ��Ē������g���ς�������ƁE�`���������ƁB |
| ���� |
���k����̓I�Ɏ��g�ސl���E���a���� |
������o�����w�Z |
1997�N����p�����Ă���w�N���Ƃ̌��n�K��w�K����������A���k����̓I�Ɏ��g�ސl���E���a����Ɏ��g��ł���B�����āA���k���w���Ƃ⊴�������Ƃ��N���X�Ɏ����̌��t�œ`������A���k���m�̏c����w�K��A�l���ʐM�Ȃǂ����p���āA�w�т����̏����ŏI��点��̂ł͂Ȃ��A�U��Ԃ�A���L���邱�Ƃł��[���w�тɂȂ���B |
| ���s |
�������傤�ԁA�������ɂ����`�L���ȏo���ʂ��ċC�Â��A�w�сA�Ȃ���` |
�s����K�X���w�Z |
�u�n��̎d�����炵�A���j�Ɋw�Ԓn��w�K��푈�ɂ��Ă̊w�K������Ɉ�����ݏo�������ƂÂ���ɂȂ��Ă��邩�v�u�q�ǂ������������̂��炵�⍷�ʂ̌��������߂邱�Ƃ�ʂ��āA���ԂƂǂ̂悤�ɂȂ����Ă��������v�u���Ƃ�n�����邱�Ƃ��狳�E�����g���ǂ̂悤�ȋC�Â����������̂��ǂ����ȕϊv�����̂��v�ɂ��ĕ���B |
| ���� |
���Ɛ��Ƃ��ē`���������Ɓ`�w�������N���������Ɓx���㉉���ā` |
�s���슋�����Z�莞�����Ɛ��̉�
|
�S�����ފw���w�Z���j�Ƃ��Ă����s���슋�����Z�莞���ɒH�蒅�������́A���̓슋�Ő�������ς��邱�Ƃ��ł����B���̑傫�Ȃ��������������̎��Ƃ������B������ʂ��ĕ����o�g���k�̂��Ƃ�{�C�ōl���邫�������ɂȂ����̂ł���B���̌�A���Ɛ��̉�u����v�ɎQ������悤�ɂȂ������A���̊����͂₪�āu���k�Ɍ����ĉ������㉉���悤�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă������B����͓�x�ڂ̏㉉�ƂȂ����w�������N���������Ɓx�𒆐S�ɕB |
| 2 |
���s����r���w�Z�̈�� |
���� |
�v����`���A�S���Ȃ������A�Ƃ��ɋP�������������߂����� |
���n�s���؉������w�Z |
�l������n��̕��Ƃ̌𗬂�ʂ��āA���a�̑����ӂ邳�Ƃ̂悳��m��A���M�������Ďv����`���A�Ƃ��ɋP�����������̈琬���߂����āA���g�B |
| ���{ |
�������ɂȂ��镔�����w�K���`�C�w���s�̂Ƃ肭�݂���` |
�L�ˎs����w�Z |
�����̎v���������ɁA���ɂ͗͂ʼn������悤�Ƃ���`�B���w�����͒��ԂƂ̃g���u�����₦�Ȃ������B�������A�ی�҂⒇�Ԃ̎v���ɂӂ�邱�Ƃŏ��������������߂Ă����B�����āA���������߁A�s����ς��Ă������B |
| ��t |
���������̊����Ɖۑ� |
�������a���猤���� |
�������a���猤����͖@���ꂽ��Ƀ����̕��Ƌ������A�q�ǂ��𒆐S�Ƃ��ĕ������ʂ��l���钆�ł��ꂼ�ꂪ���܂��Ă������Ɛݗ����Ă���P�S�N�B�N�E���Z���̎Q�����镔�����ł͎����̕������l���邱�ƂŁA�����̍��ʐ��ɋC�Â�����A�����ǂ߂Ȃ�����������������L���Ɍ�����肷��p��������B�����̐�y�Ƙb����������ł́A���ꂼ�ꂪ�����̘b������悤�ɂȂ��Ă����B���̊�����[�߁A�L���邽�߂ɉ��P�̎w�E�������B |
| ��� |
�u�搶�A�������ĉ��ł����v�`�����グ���q�ǂ���A�����ɍ��葱���邱�ƂŁ` |
����s�����s���w�Z�@ |
�U�N�O�A�o�g��`�����s����Ԃ��Ă����u�l�Ɠ��������̒��Ԃ͂��Ȃ��̂ł����v�Ƃ̔����B�q�ǂ���𗧂��グ�邱�Ƃ����̒��ɉۂ������Ă����B�V�����E��ŏo������h�̋�Y�Ɍ����������������X�B�u�������ĉ��ł����v�Ɩ₤����B�r�Ƃv�̂R�l�ŃX�^�[�g�������u�R�̉�v�i�q�ǂ���j���������E�E�E�B���������ꑱ���Ă���B |
��
�R
��
��
�� |
�i
�H
�E
�w
��
��
�� |
1 |
���{��������x���w�Z�̈�� |
�F�{ |
���Ɨ������̂�����A����Ȃ��Ă������̂�����B���̈Ⴂ������Ƃ���ɍ��ʂ�������B |
�������������w�Z |
�����獂���w�Z���A�w�x�������ޓ͂���o�����B�u������t�������A�S�̓I�ɂ킩��ɂ��������B�x�������x�͖������ƈႤ�l���ł͂Ȃ����B���Ɨ����ɂ��Ăق����v�ƌ��ی�ҁB���x�ɂ��鍷�ʂ��������Ȃ���A�~�ϑ[�u�̎������߂�������g�̕B |
| ���{ |
�݂�ȂƂR�N�����`����F�ߍ�����N���X�ց` |
��؎s���������w�Z |
�N���X�~�[�e�B���O�����������Ɏ��������߁A��肪���鎩���������悤�ɂȂ����`�D����Ȃ`�̎p�́A����̎q�ǂ����������������ߒ������������ɂ��Ȃ����B���ꂩ��̎����̐��������`�ƂƂ��ɍl�����Q�N�Ԃ̎��H�ɂ��ĕ���B |
| �ޗ� |
�肢���Ȃ��邽�߂Ɂ`�O��w�Z�ƂЂ܂��̉ƁE����ƕ����̘A�g�` |
�O����O��w�Z�@�Љ���@�l�Ђ܂�� |
�O��w�Z�̒����炤�܂ꂽ�u�Ђ܂��̉Ɓv�B��Q�����q�ǂ��������Ƃ��Ɋw�тƂ��ɐ����Ă����w�Z�E�n��Â�����߂����āA����ƕ��������݂��̊_������炸�Ɏ��g��ł������Ƃ���܂��B |
| �V�� |
���Ƃ��Ă������Əo�����B |
�����C�m�����w�Z |
���ƌ��������葱���邱�Ƃ̑�����w���Ă���������k�������B���̌�A�]���A�A�E�S�������ĂR�N�B�����̐��k�������ŏA�E���Ă����B�w�Z���̓��ꉞ��p���ɂ͏����Ȃ����܂��܂ȃv���t�B�[�������������k������B�j�����̈�l���B�݊w���ɐS�z���ꂽ���Ƃ��A���Љ�ɏo�Ă��猰�݉����Ă䂭�B��ЂƂ̊W�A�E��̐l�Ԃ̗����A�Ƒ��̂��肩���A�x���̋��E�ɂ���^�C�v�̓���B�j�Ƃ��������k�Ƃ̊W������Ȃ���A�l���Ȃ�������݂��n�߂��B |
| 2 |
���s���k�������w�Z�̈�� |
���� |
�����̖��������߂Ɂ`���ׂĂ̐��k�́u�w�сv��ۏႷ��l�������ڎw���ā` |
�����ܔ������w�Z |
�o�ϓI�Ɍ������ɒu����Ă��鐶�k�������A�����]���関�����Ă�����悤�A����܂ł́u�w�т̕ۏ�v�̎�g�i�^���j�̊w�K��ʂ��āA�u�w�т̈Ӌ`�v����������l���w�K�̎�g�̕B |
| ���� |
�u���̒n����������Č�����q�Ɂv�`�n��ƕ�̊肢����` |
��s��w�Z |
�u���̒n����������Č�����q�ɂ������v�Ƃ����n���ی�҂̊肢�Ǝx���̒��ŁA�����܂������������Ă������߂̊w�́A���ʉ����ɗ����������͂����邽�߂ɁA����q�ǂ���̒��ԂÂ����l���w�K�A����I�ȕ���Ɏ��g��ł����B |
| ���s |
�q���E�̐������x�������`�n��ƂȂ��邱�ƂŌ����Ă������Ɓ` |
�s���������w�Z |
���w�������肾���A��l������悤�Ȕ����B��e���s�݂ł��邱�Ƃ������A�ƂɋA�炸�ɐS�z��������悤�ɂȂ�B���낢��Ȑl�Ɗւ������A��������肳���o���������邽�߂ɁA�s���𗬃Z���^�[�ŊJ���ꂽ�u���ǂ��H���v��u�q�ǂ��ُm�v�ւ̎Q���Œn��A�g��ʂ��ċ��ꏊ�Â���A�������ɂ��邱�Ƃւƌ��т������H�B |
| ���� |
�u�ڂ��̓o�J���Ǝv���Ă��܂����v�`�l�ƌ����������Ƃ́A�����ƌ����������Ɓ` |
�b��s���b�ꒆ�w�Z�@ |
���P�̓~�A�s�҂ɂ�莙���{��{�݂ɓ������A�{�Z�ɓ]�����Ă����`�ƕ҂Ƃ̊ւ��B�f�̂܂܂ł`�Ɗւ�钆�ŁA�\�͂��l�ɑ���`�̕s�M���ɒ��ʂ���B�`�̏������������`�̏��~�߂Ȃ���A�ւ�葱�������ŁA�l�����������Ƃ����B |
| ���� |
��l�̐��k���狳��������̂����� |
�s������H�ƍ����w�Z�S���� |
�{�݂���ʂ����k�����̌����������ƌ��������Ȃ���A���Ƃ��w�Z�ɓ��ݗ��܂点�����Ɗւ���Ă��Ă��邪�A���̗���͂Ȃ��Ȃ��ς���Ă����Ȃ�������B����Ȓ��ɂ����Ă����͂�邬�Ȃ��ւ��𑱂��Ă������Ǝv���Ă���B����͑O�C�Z�őފw���Ă������ݓ����N�l�S���̐��k�Ƃ̊ւ�肪�����Ă��ꂽ���Ƃ����邩�炾�B�������猩���Ă��鎄�̉ۑ�A�w�Z�̉ۑ�A����̉ۑ�A�Љ�̉ۑ�𖾂炩�ɂ��Ă��������B |
| 3 |
���R�w�@�����w�Z�J���^�x���[�z�[�� |
������ |
�u�����̎q�ǂ��́A�s���ꂪ�Ȃ��v�`�����Ń~�[�n�b�P�[�i�����j�̐��_���` |
�^�_�����^�_���w�Z |
�҂́A���w���ƌ�̐i�w��Ƃ��ē��O�̓��ʎx���w�Z�����߂��Ă���q��e�̎v����m��B�����āA�����v�������e�����A������n��A�s���Ƃ��Ȃ���Ȃ���A�u�s���ꂪ�Ȃ��v�q�ǂ��������n���̍��Z�łƂ��Ɉ���߂̂Ƃ肭�݂��n�߂�B |
| �F�{ |
�u����Ȃ��E�����Ȃ��E��o���Ȃ��v�F�{���ƍ��Z�̎�g |
�����F�{���ƍ����w�Z |
�w�Z�ł̈�т����u����Ȃ��E�����Ȃ��E��o���Ȃ��v��g�̒��ŁA�ᔽ����ɗ����オ���Ă�����݂���̎p����A�K���̗p�I�l�Ɍ����ċ��E�����g�������ʂւƗ����オ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁA�l������̒~�ς̑�������w��ł������B |
| ���� |
�u����A���[�_�[��邯��v�`����������M�������A���S���ċ��͂ł���W�c�Â�����Ƃ����ā` |
�����s�����쒆�w�Z�@���������������w�Z |
����������M�������A���S���ċ��͂ł���W�c�Â���Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�{�����e�B�A�����ɂ��A�ϋɓI�Ɋw�Z��n��ɍv�����悤�Ƃ����g��ʂ��āA���k�̎����ӎ������߂�ƂƂ��ɁA�������Ă����͂��琬����B |
| ���{ |
��������˂�`�u�ς��v�ƌ��߂����̐�Ɂ` |
���Ύs����쒆�w�Z |
�W�c�̒��ŁA���܂��܂ȕs���₵��ǂ�������Ȃ��琶�����Ă���q�ǂ������B���ԂƂ̂Ȃ���̒��Ŏ������J���A�ۑ�ƌ��������A�����������Ă������`�ƒ��Ԃ̎p��ʂ��āA�i�H�ۏ�Ƃ͉����Ɩ₢�������Ƃ肭�݂���܂��B |
| ���s�{ |
�u����ł������撣��I�v |
�����s���j�R���w�Z |
���ƒ��Ɏ��ꂪ�₦���A�w�K�ʁA�����ʂɉۑ�̂��鐶�k�������B���̐��k�̐i�H�����������邽�߂ɁA�݂�ȂŌ����͂��A��g���j�����肵�A���H���Ă������B���̉ߒ��Ŋw���Ƃ́A�ʎx�������ĉƒ�A�g�̑���ł������B |
| 4 |
���s�������w�Z�̈�� |
�啪 |
�����Ȃ��Ɓ@�ł��邱�Ƃ���@���������`�ڂ̑O�̎q�ǂ����@�q�ǂ��炵�����S���Ă̂т̂тƉ߂����鎞�Ԃ��` |
��ʎВc�@�l�@�q�ǂ��̂�����l�b�g���[�N�啪 |
�q��Ă��݂�ȂŒS���A�Ȃ���̒��Ŏq�ǂ��ɐl�Ƃ̉��������ꏊ������A�w�K�x���E���H���E�̌������B�����e�Ɏ��ԓI���_�I��Ƃ���A�ʋ��e�Ɏq��Ă̊�тƐӔC���A�����q�ǂ��Ɉ��S��ۏႷ��ʉ�𗬎x���B |
| ���m |
���k����w�ԁ@�`A�N�̕ϗe��ʂ��ā` |
�{��s�������u���w�Z |
�`�w�Z���ς��`����I�ɕϗe�����Q�N���̈�l�̐��k�̐�����ʂ��āA�u�`�[���v�Ƃ����ӎ��������Đ��k�𗝉����邱�Ƃ�A�A�v���[�`���邱�Ƃ̑�����w�P�N�Ԃ̎�g�B |
| ���s |
�u�����ɂ����Ȃ����̂�厖�ɂ������v�`�����Ƃ̏o�����w���Ɓ` |
�s������k���w�Z |
�؍��E���N�Ƀ��[�c�̂��鐶�k�Ƃ̏o��B�B�`�����j������ʂ��Ď����̃��[�c�𖾂炩�ɂ���̂�������v�����N���X�݂̂�Ȃɒm���Ă�������B�w�i���ӎ����Ȃ��Œ��ǂ�����̂ł͂Ȃ��A�킩���������Œ��ǂ��ł��邱�Ƃ�����ƋC�Â����ꂽ�R�N�ԁB�u�m��Ȃ����Ƃ̕|���v�Ɓu�m�邱�Ƃ̑���v�ɉ��߂ċC�Â����Ƃ��ł������H�B |
| ���� |
�u�Z���Z�A���A���������Ȃ��E�E�E�B�v�`���̎d���͂Ȃ��葱���邱�Ɓ` |
�����Γ�_�ƍ����w�Z |
�r�n�r������o���Ȃ����k�ɑ��āA�݊w������]�w�A���ƌ���ւ������������A�C�ɂȂ����玩�炪�����A�Ȃ��ł������Ƃւ̋C�Â��ƁA�i�H���J�����k�ւ̎x���Ɋւ���{�싳�@�̎��H�B |
| �ΐ� |
���b����Ƃ́u������ׁv��������w���� |
�����a�@�@�\�@�㉤�a�@�@��Õ������n���ØA�g�� |
�c���Ƃ��ɓ�a�������A20�N�ȏ�̗×{��]�V�Ȃ����ꂽ���b����́A�u������ׁv������ʂ��Ď�����U��Ԃ�A�Ԃ��邱�ƂŁA�����̐������ɂ��Ė₢�n�߂��B�����g�����Ɏ��g�ޒ��ŁA�w���ƁA���ꂽ���Ƃ����B |
��
�S
��
��
�� |
�l
��
�m
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�� |
1 |
����w�痢�R�L�����p�X (��3�w�Ɋٓ�)�@A201 |
�F�{ |
�������͂�����̂��� |
����������������x�� |
����܂ł̉���^�����ӂ肩����A��l�����̕����u�t�̓��v�u���Ɓv�u����ꂽ���ʁv�Ȃǂ����킵���m�邱�ƂŁA�ւ�ƗE�C��n�肾���A���ʂ��������邽�߂̒n��Â�����߂����B |
| ���� |
�u�O�L�͂ЂƂv�`�l�����狳�ޏW�E���ŋ��̍쐬���Ƃ����ā` |
�O�L�s����ψ���l������� |
�u�����̑升���v�ɂ��V�����̒�����ɂȂ��Ēa�������V�s�ɂ����āA�l������������߂�ɂ͎s���̐l���ɑ���ӎ��i�����傫�������B���̏̂Ȃ��q�ǂ����܂ގs���S�̂̐l���ӎ��̌����}���̎�i�Ƃ��āA�ۈ�E�w�Z���瓙�̏�ł͎������k�̓��ꐅ���̐l���ӎ�����ނ��ߎs�Ǝ��̐l�����玆�ŋ��E���ޏW���쐬�����B���̋��ނ̊��p��ʂ��Ďq�ǂ������ɐl������������߂Ȃ���A�ی�҂�n����������l������Ɏ��g��ł���B |
| �ޗ� |
�s���[���Ɏ��g��Ł`����11���́u�l�����m���߂������v�̂������` |
�ޗnj��s�����l���E���a���[���������i�{���A�����c�� |
1988�N�ޗnj��s�����l���E���a���[���������i�{���A�����c��������ꂽ�B�҂̕����������ւ̎v���Ɓu�[���A���v�����Ɏ��鎞��w�i�A�����̑S�s�����Ől���E���a�������Ɍ������u�[���v�Ɏ��g��ł���l�q�����B |
| �O�d |
���̋��ꏊ�A�����Č��_ |
���q�����N�� |
���͕������ʂƂ͎��R�Ȍ`�ŏo��A�A�搶�A�F�B�A�Ƒ��A�n��̐l�Ɏ���Ă������߁A���ʂ��Ĕ߂����v���������o�����Ȃ��B�v���U�w�K��ʂ��āA�搶��n��̐l�ɕ������ʂɂ��ċ��������A�ꏏ�ɍl�����肷�钆�ŁA�l�����o���Ă����B�������A���������ʼn����ԈႢ�Ȃ̂��悭����Ȃ��B�����̒��ɂ����ʐS������̂�������Ȃ��B����Ȏ����ɍ��A�����ł��A���̂悤�ɂȂ����Ă���̂��A�����̎v�������B |
| 2 |
����w�痢�R�L�����p�X (��3�w�Ɋٓ�) A202 |
���Q |
�w�Ԃ��ƂŐl�͕ς���`�l���E���a�����ʂ��Ă̏o�����` |
�l�������s�l�����狦�c�� |
���E���w�Z��PTA�l���E���a���畔���Ƃ��Ċ������钆�ŁA�����̏o��Ɗw�т�����A���̌o������u����w�т����v�Ƃ��������v���ɕς�����B�w�Z�ƘA�g���Ȃ��炫�ߍׂ₩�ȕی�Ҍ[�������H���Ă���B |
| ���� |
���w������P�O�O�܂Ł@�N�������݂₷���܂����߂����āI�`��R���l���E���a��菬�n�捧�k��̎��g�݂𒆐S�Ɂ` |
��R���l���E���a���琄�i���c�� |
�Â��A�Â��A���������Ȃ��A���������E�E�E����ȍ��k���̃`�F���W�I�ʉۑ��ӓ|�̍��k����A���ՓI�ȃA�v���[�`����̏��n�捧�k��ցB�����钆�ŁA�l���̊w�тɑ��钬���̈ӎ��̕ϗe���o�Ă����B |
| ���� |
�j���ۈ�m����݂��j������ |
�Љ���@�l�݂����@�c�ۘA�g�^�F�肱�ǂ��������� |
�ۈ�ƊE�ɂ��ߔN�j���ۈ�m���������Ă������A�܂��j���ۈ�m�ւ̔F�m�x�͒Ⴍ�A�Ό����j���ۈ�m�̏A�J��j�߂Ă���ʂ�����B�܂��A����ɂ����ẮA�j�����ƈӎ����j�����킸�ۈ�m���ɂ��������Ă���B���ʂɂƂ��ꂸ�ۈ�m���݂��ɔF�ߍ����A���d���������Ƃ��A�S�g�Ƃ��Ɍ��₩�Ȏq�ǂ�����ނ��߂ɂ͂������ł���B�����̎�g��i�߂邱�Ƃɂ��A�Љ�ɑ��݂���E�Ƃ̒j���I�ʈӎ��@���A��ɑ����j���ۈ�m�̓�����ׂɂȂ肽���B |
| ���s |
�����ƃP�A���߂����ā`�n��̎q�ǂ��̋��ꏊ�Â���` |
��������������{�A����]�x�� |
�q�ǂ��̋��ꏊ�Â���̂��߁A�q�ǂ�����i����A�q�ǂ��H���j���H�v���Đi�߂Ă���B�]������̒n���̎q�ǂ������ł͂Ȃ��A����̎q�ǂ��������ۂ��邱�ƂŔ����ʂ́u�W�ҁv����ĂĂ��������Ƃ������v���E�肢����i�߂��Ă�����g�ɂ��Ă̕B |
| 3 |
����w
�痢�R�L�����p�X
(��3�w�Ɋٓ�)�@D302 |
�{�� |
�����s�̐l���E���a����̎�g |
�����s���a���琄�i�ψ���
�@�y�X�C���w�Z
�@�����H�ƍ����w�Z |
�����s�ɂ����āA���ʂ̌�������w�сA����q�ǂ���ւ̊肢������ɂ����āA�x���i��������j�A�s���A�n�擯�����ꂼ�ꂪ�������ʂ��Ȃ������߂ɓ����������ނ��Ȃ���i�߂Ă����g�̕B |
| ���m |
�킽����ς������� |
�����s����ψ���U�w�K�U���� |
�����s�̐l�����ƂɊւ��錻��Ɖۑ�B���a�E�l������Ɋւ���Ă����l�Ƃ̌𗬁B���܂��܂Ȏ��Ƃ�ʂ��ĒS����ς������́B�l���ɌW���l�����̔M���v���ɉ����邽�߂ɉ����K�v���B�����ĉ������ׂ����B |
| ���� |
���̓����@���̂������`�����蕔�� |
��������������挧�A����O�h�x�� |
�R�O�N�O�A�Ƒ��̔����������Č����������ł������A�������̏Z��Ɉ����z�����Ƃ����܂������A�g���S������܂����B�������A�����̐l�����̉c�݂Ɨ��j�ɐG�ꂽ�Ƃ��A�����̐S�����������Ǝv�����ɕς��܂����E�E�E�B |
| �a�̎R |
���̋��ꏊ |
�⋴��Ԋw�Z |
�퍷�ʕ����ɐ��܂ꂽ50�̕҂��⋴��Ԋw�Z�ɒʂ��悤�ɂȂ��Ă���8�N�ڂɂȂ�B�҂Ɩ�Ԋw�Z�Ƃ̂ł����A�����łł��������Ԃ̘b�A�v���o�Ȃǂ����Ȃ���A��Ԋw�Z�ƕ҂̊W����U��Ԃ郌�|�[�g�ł���B |
| 4 |
����w�痢�R�L�����p�X (��3�w�Ɋٓ��j�\�V�IAV��z�[�� |
���� |
�g���s���I�}�C�m���e�B�i�k�f�a�s�j�x�����Ɓ`���F�ɋP���܂��Â�����߂����ā` |
�g���s�s�����l���ہ@
�g���s�l���u�t�c |
�Q�O�P�S�N�x����{�s�����g��ł���A���I�}�C�m���e�B�i�k�f�a�s�j�x�����Ƃɂ��ĕ���B�ŏ��ɖ{�s�����g�ނ悤�ɂȂ������������ɂ��Đ������A���̂��ƂɎ��т��@���C���ƁA�A���k���ƁA�B���������Ƃ𒆐S�ɕ���B�Ō�͂��̒��ŕ�������ƂȂ����A�ۑ�⍡��̕��j�ɂ��ďq�ׂ����B |
| ���{ |
�u�����Ȃ猾����v����u�ǂ��ł�������v�ց`�u�I���j�}�_���v�Ƃ����u�����v����݂���O���Ƀ��[�c�̂���q�ǂ������́u����v�` |
�����s�ݓ��O���l���猤����@ |
�����s�ōs���Ă���O���Ƀ��[�c�̂���q�ǂ������̏W���u�I���j�}�_���v�́A�n��̎q�ǂ��������n�܂����B���w���̕��ł́u��荇���v���Ƃ𒆐S�ɍs���Ă���B����܂ł��ӂ肩����A���̐��ʂƉۑ�ɂ��ĕ���B |
| �ޗ� |
�l������̎�_���������邽�߂� |
�ޗǎs�l�����琄�i���c��
�@�Îs���j������ |
����܂ł̐l������̃C���[�W������_�����������@�Ƃ��āA�ޗǎs�l�����琄�i���c��ƘA�g���ČÎs���j��������g��ł����n��ɂ���l���ɂ��������j�X�|�b�g������t�B�[���h���[�N�u�l���䂩��̒n�߂���v�̎��H�B |
| �O�d |
���a�n��ɐ��܂��39�N�`����܂ł̂킽���@���ꂩ��̂킽���` |
�_�O�n��q�ǂ��l�������琬���c�� |
�q�ǂ������ɂ͎����̈�����n����B���Ăق����Ȃ����A���ɂȂ��Ăق����Ȃ��Ǝv���Ă���B���̂��߂ɁA�q�ǂ��ǂ������Ȃ����Ă��Ăق������A���������ɑ��k�ł���l����l�ł�����A����ȊW�������Ă����Ăق����B�e���q�ǂ����������ɂ��Ă����ƒm���āA���炩�ɂ����������ł��邱�ƁA���������͉������������Ȃ��Ă����Ƃ������ƁA�܂������O�������Ă��ꂩ��������Ă����������Ƃ��A���̎��̎v���ł���B |
| 5 |
��㋳���w�V�����L�����p�X����ΰ� |
���s |
�u�ڂ��̉ߋ��̓��L�ł��ˁv�`�����w���̖����ɂނ��ā` |
���s�������E���{�ꋳ���A���� |
�w�Z�ɂقƂ�ǂ����Ȃ������Q�O��̎�҂��A�ߋ��̂��Ƃ���L�̂悤�Ɍ�邱�ƂŁA�����̐l�������߂����Ƃ��Ă���B����ɂ͎����w�����|���Ă��������╶���ɕ����Ƃ��낪�傫���B�����w���̖����ɂ��čl���Ă��������B |
| ���s |
Minami���ǂ������ɎQ�����ā`�w�K�x���Ƌ��ꏊ�Â�����߂����ā` |
Minami���ǂ����� |
���s������̓쏬�w�Z�ł͊O���Ƀ��[�c�̂���q�ǂ����S������B�P�e�ƒ�������A��Ԃ͎q�ǂ������ʼn߂������Ƃ������B�w�Z�A�n��Љ�ANPO����������x�����f���Ƃ��Ă̊w�K�x���Ƌ��ꏊ�Â�����߂�����g�ɂ��Ă̕ł��B |
| ���� |
���܂��܂Ȍ������Ă���l�ƌ��������A�n�攭�̗וۊقł��肽���`�ӂ����human-rights story���Ƃ߂āE�E�E�` |
�L�����n�摍���Z���^�[ |
�n�摍���Z���^�[�E�וۊق̂ӂ��̎�g��ʂ��āA�Ȃ����Ă���Ă���ӂ���̏��������ʂ�����������A���ꂼ�ꂪ�������z����`���Ă����B����Ȕޏ������ƌ��������Ă����ׂ��וۊقł��肽���Ƃ����Ӗ�������������B |
| 6 |
�a��s���x�H���w�Z�u�� |
���Q |
�Ⴊ���̂���q�����ň炿�A�����Ȃ����炵�Ă������߂� |
NPO�@�l�㓇�|�b�v�R�[���̉� |
�Ⴊ���̂���q�炪�A���܂��������ŁA���ƂȂɂȂ��Ă������A��炵�Ă������߂ɁA�ꂽ�������\�N�ɂ킽�芈�����Ă������Ƃ��A���ɂǂ����t���A�l�X�̈ӎ����ǂ��ς���Ă������B�o�����犴�������Ƃ����B |
| ���m |
��D���Ȓn��̖����̂��߂Ɂ@�`�ۈ�E�w�Z�E�N�c���Ȃ��邱�ƂŎq�ǂ������ɓ`���������`�@�@�@ |
�썑�s���������N�c |
���������N�c���n����O�łǂ̂悤�Ȋ��������Ă���̂��B�q�ǂ���������Ă邽�߂ɁA�s���ق�ۈ珊�A�w�Z�Ƃǂ̂悤�ɐ[����������Ă��邩�B�܂��A���ʂ̌����Ɍ����������g���ƂŁA�����������n���q�ǂ������̗͂ƂȂ邽�߂ɁA�����Ă��銈�����e����܂��B |
| ���� |
�������̐����i���炵�j�ƌ��@�`�m��Ȃ����Ƃ�m��Ƃ��납��` |
��ˎs���l���w�Z��l���[�����i�ψ��� |
�Q�O�P�T�N�ɏ��l���w�Z��l���[�����i�ψ���̊w�K�����Ƃ��āA�u�������̐����i�l���j�ƌ��@�`�m��Ȃ����Ƃ���m�邱�Ƃ���`�v���e�[�}�Ɏ��{�����w�K��ɂ��ĕB |
| ��� |
���k�n��̓��a�s���ł���ɍR���� |
�{���s�l�����猤���� |
�P�A�퍷�ʓ����҂̐����s���ɓ͂������B�@
�Q�D�u�l�����d�Љ�𐄐i����s���̉�v�̎�g�B
�R�D�c��ɂ����ē��a�s���S�ʔp�~�̖��_�𖾂炩�ɂ��A����̕������ʂ��Ȃ����{���Nj�����B�@�@�@�@�@ |
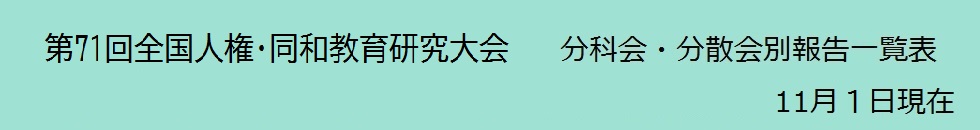 �����ł͂���܂���B���͂P�P���Q�T���i���j�Ɍ��肵�A�ߌエ�m�点���܂��B
�����ł͂���܂���B���͂P�P���Q�T���i���j�Ɍ��肵�A�ߌエ�m�点���܂��B